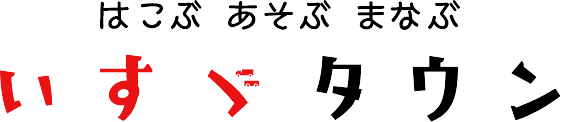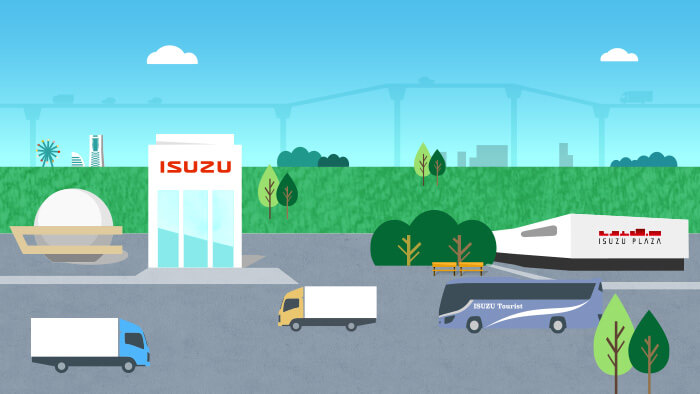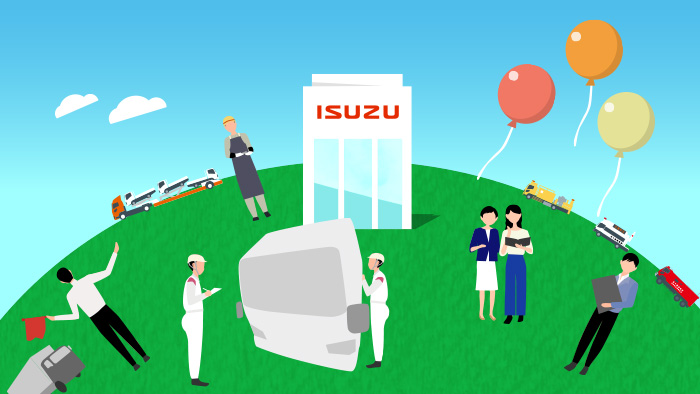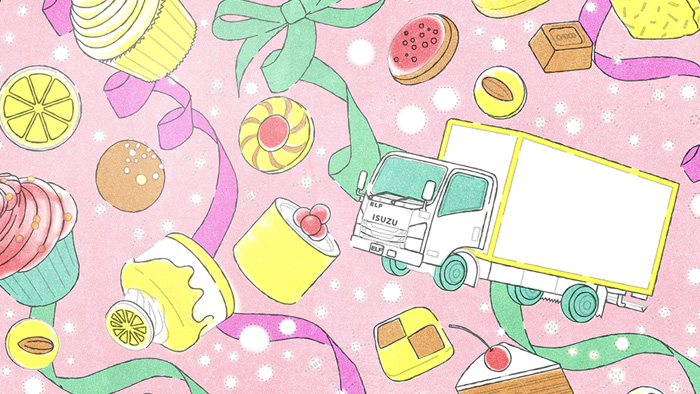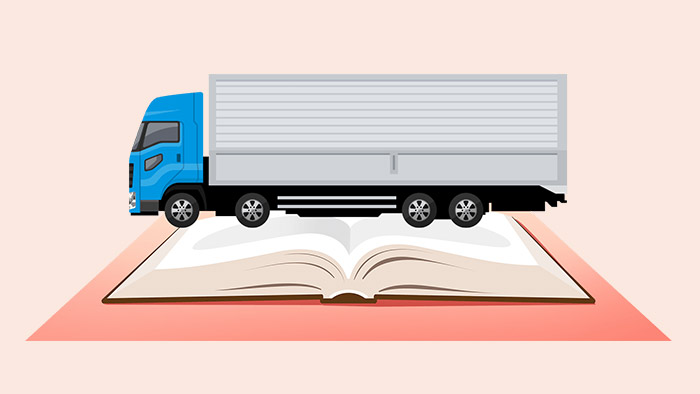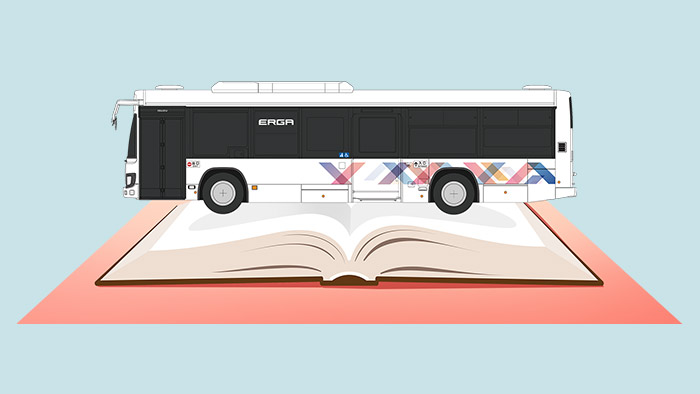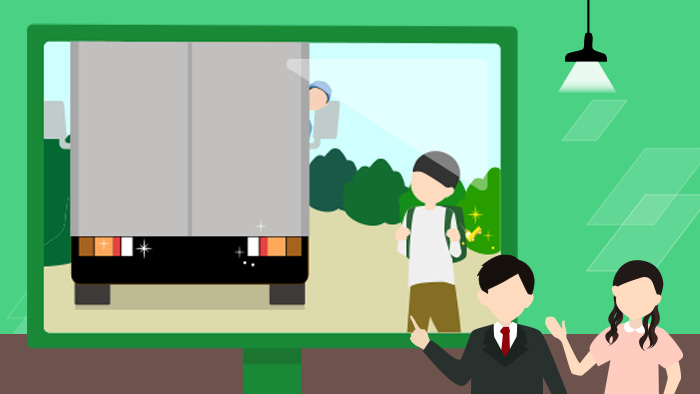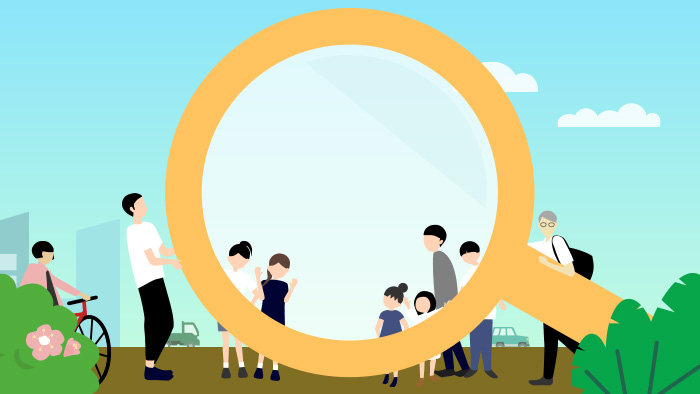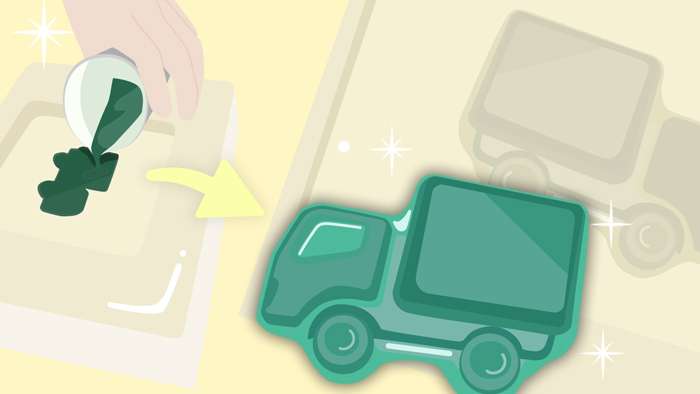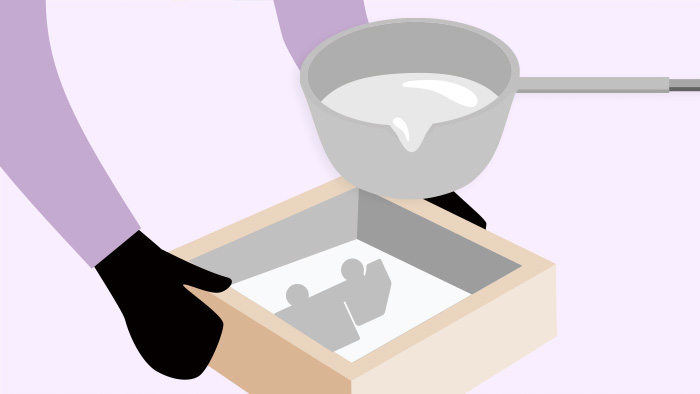「はこぶ」の世界をささえる人々


今回は特別編(へん)として国立極地研究所の南極地域観測隊の一員として南極に派遣(はけん)された経験(けいけん)を持つ、4人のいすゞ社員のみなさんに話を聞きました。いすゞは、1956年の第一次南極地域観測隊から今まで、継続(けいぞく)して南極に社員を派遣しています。
人物紹介

- 白濱政典さん第53次南極地域観測隊隊員

- 森戸毅さん第63次南極地域観測隊隊員

- 半田英男さん第39次・第43次・第48次南極地域観測隊隊員

- 栗崎高士さん第44次・第55次(夏隊)南極地域観測隊隊員
南極に行くと決まったときはどんな気持ちでしたか?
白濱さん
部署(ぶしょ)に南極観測隊OBの先輩(せんぱい)がいて、いろいろな話を聞いていました。いつかは行ってみたいと思っていたので、決まった時はうれしかったです。ただ子どもが生まれたばかりだったので、どうしようかと少しまよいもありました。結果的には妻(つま)や家族が応援(おうえん)してくれて、行ける環境(かんきょう)を整えてくれたのでありがたかったです。
森戸さん
いすゞには南極に行ったことのある先輩たちがたくさんいるので、わたしもいつかはと思っていました。実際(じっさい)に決まった時はうれしさ半分、不安も半分でしたね。でも実家の母がよろこんでくれたので、親孝行(おやこうこう)になってよかったです。
半田さん
わたしはこの4人の中では一番年上で、はじめて南極に行ったのは1997年、32さいのときでした。30代になってお話をいただき、候補(こうほ)に決まったときは体がふるえましたね。うれしかったです。そのときをふくめて合計3回、観測隊員として南極に行きました。
栗崎さん
わたしはいすゞから南極に行った人間としては歴代(れきだい)最年少。26さいのときに南極に行きました。候補としては3番目だったのですが、上位の候補者がいろいろな事情(じじょう)で行けなくなって順番が回ってきたのでラッキーでした。実は10月ごろからコタツを出すほどの寒がりなので、まわりからは本当にだいじょうぶ?と心配されましたね(笑)
南極はどんな場所でしたか?
森戸さん
南極に着いたのは12月で、季節は夏でした。昭和基地(きち)周辺の気温はマイナス1度くらいで、これは東京の真冬でもあるくらいの気温です。だから南極に着いたときは、想像(そうぞう)していたよりもあたたかかったです。

白濱さん
昭和基地周辺は、夏は雪もそれほど積もっていなくて地面が見えているところもあります。なので、着いたときはなんだか建設現場(けんせつげんば)にきたような印象(いんしょう)でしたね(笑)
半田さん
昭和基地には荷物をはこぶためのトラックもたくさんありますから、夏の昭和基地周辺はみなさんがイメージする南極の風景とは少しちがうかもしれませんね。


夏の昭和基地はまるで建設現場のよう
栗崎さん
3人とちがって、わたしは昭和基地ではなくそこから約1000kmもはなれた場所にあるドームふじ基地に派遣されました。ドームふじ基地は昭和基地よりもとても寒くて、最低気温はマイナス79度を記録したこともあるくらい。きっとみなさんがイメージする南極ですね。
白濱さん
ドームふじ基地はものすごく過酷(かこく)な環境ですよね。昭和基地は南極大陸から4kmほどはなれた東オングル島という場所にあり、ドームふじ基地よりはあたたかいんです。
栗崎さん
わたしが行ったドームふじ基地の周辺は、雪と氷の世界です。南極大陸の内陸部の何もない真っ白な場所にヘリコプターでおりました。はぁーっと息をはくと、自分の息がこおるシュワシュワという音が聞こえるくらい寒いんですよ。わたしたちはその音を「天使のささやき」なんて言っていました。

ドームふじ基地にて。自分の息でまつげがこおってしまうほどの寒さです。
森戸さん
昭和基地周辺も冬の寒い日はマイナス30〜40度くらいまで下がります。息をすると肺(はい)の中に冷たい空気が入ってきてキュッとなります。でも基地の中は暖房(だんぼう)があるのでTシャツと短パンですごせるくらいあたたかいんですよ。
南極での仕事について教えてください。
白濱さん
トラックや雪上車、ショベルカーなどいろいろな車両の整備(せいび)が主な仕事です。故障(こしょう)の修理(しゅうり)はもちろんですが、大切なのは故障する前の小さな不具合を見つけて大きな故障にならないようにすること。オイル交換(こうかん)なども定期的に行っています。

半田さん
車両だけでなく、発電機のエンジンのメンテナンスもわたしたちの仕事です。暖房をはじめとして、南極での生活や仕事に必要な電力はディーゼルエンジンと発電機で作られています。
栗崎さん
ドームふじ基地の発電機はいすゞのディーゼルエンジンが使われていました。マイナス70度の世界ですから、発電機がこわれてエンジンがかからない、電気がつくれないというのは「死」につながる危険(きけん)な状況(じょうきょう)。だから南極でのエンジンのメンテナンスは、命をささえる仕事なんです。わたしは当時の隊員たちから「守護神(しゅごしん)」とよばれていました(笑)
森戸さん
いすゞの人はなんでも直せると思われているんですよね(笑)だから、車両や発電機にかぎらず、機械がこわれると声がかかります。そうは言っても部品がすぐ手に入るわけではないので、あるもので工夫してなんとかするしかないこともよくあります。
白濱さん
わたしが南極にいったときは、氷河(ひょうが)の氷のあつさをはかるための掘削装置(くっさくそうち)がこわれていました。直さないと研究ができないのですが部品が足りなくて、基地にあった高圧洗浄機(こうあつせんじょうき)の部品を使ってどうにか動かしました。研究者のみなさんがすごくよろこんでくれて、論文(ろんぶん)にわたしの名前を記載(きさい)してくれたんです。

森戸さん
わたしもスノーモービルがこわれたのを直しましたね。南極生活の終わりくらいに、スノーモービルが全滅(ぜんめつ)したんです。スノーモービルはいすゞの製品(せいひん)ではありませんが、日本のメーカーに問い合わせたりして情報(じょうほう)を集めて、にたような部品をさがして無事に動いたときはすごく達成感がありましたし、よろこばれましたね。

半田さん
前の年の隊員から連絡(れんらく)もあるので、必要な部品は持って行きますし、足りなくなりそうなものを予想して準備(じゅんび)はします。いすゞ製ではないものも直すので、南極に行く前に他の会社で研修(けんしゅう)をしてもらうこともあります。でもどんなに準備をしても想定外のことが起こるのが南極ですね。大変だけど、だから面白い。あきらめてしまうとそこで終わりなので、どうにかなおそうとねばります。
栗崎さん
日本から荷物(にもつ)と人を運んでくる南極観測船「しらせ」 が南極に来るのは1年に1回だけ。「あの部品が足りないから買ってきて」なんて言ってもとどくのは1年後。だからかぎられた物資(ぶっし)の中でなんとかするしかないし、どうにかするのがエンジニアとしてのプライドだったりもします。
ほかの人の仕事を手伝ったりもするのですか?
半田さん
仕事はみんなで協力して行います。観測隊は基本的に、各分野の専門家(せんもんか)は1人か2人しかいません。その人たちがリーダーになって、他の隊員が協力し合って仕事を進めるわけです。昭和基地の建物や施設(しせつ)を建てたときも、建築の専門家がリーダーで実際(じっさい)に作業するのは研究者の先生たちやわたしたちのような他の分野の専門家たちです。みんなで協力し合って仕事をなしとげるのが観測隊の特徴(とくちょう)です。




白濱さん
気象観測など研究の手伝いもしますし、反対にわたしたちの専門である車両整備を他の隊員に手伝ってもらうこともありました。だから南極での毎日はすごくいそがしかったですね。
森戸さん
わたしはペンギンの巣を観察するための小屋を立ち上げる作業を手伝いました。自分の担当(たんとう)の仕事以外にもいろいろな経験(けいけん)ができるのは、観測隊の面白いところだと思います。
半田さん
わたしも隕石探査(いんせきたんさ)チームに車両担当として同行して、隕石をさがしに行きました。南極は、たくさん隕石が見つかるんですよ。
栗崎さん
ドームふじ基地では、氷の層(そう)をおよそ3000メートルの深さまでほりぬいて取り出すお手伝いをしましたね。取り出した氷は「氷床(ひょうしょう)コア」とよばれます。それを分析(ぶんせき)すると、過去(かこ)の地球の気候変動の様子などがわかるんです。そのときは、およそ72万年前の氷が手に入りました。

南極での仕事や生活をともにした道具。厳しい環境に適した道具が支給されます
南極ではどんな生活をしていたのですか?
森戸さん
自分の仕事のほかにも、共同生活をスムーズに送るためのいろいろな係があります。隊員はそれぞれの係に所属(しょぞく)して活動します。基地での生活が楽しいものになるように企画(きかく)を考えるレクレーション係や、かべ新聞をつくる新聞係、映画(えいが)係やソフトクリーム係などもありましたね。

白濱さん
1年以上同じメンバーですごすので、みんな少しでも楽しくユーモアを持って生活しようとするんです。氷山の上から流しそうめんをしたり、雪の上でサッカーやソフトボールをしたりもしましたね。レクリエーション係が中心になってアイデアを出します。

栗崎さん
ドームふじ基地にいたのは、わたしをふくめて9名の隊員だけ。昭和基地には3~40人がいますが、こちらは9人しかいないのでそれぞれの役割(やくわり)も大きくなります。標高3810メートルの高地で、物資も昭和基地よりもさらにかぎられているし、自分勝手な行動をする人が1人でもいたら命が危険。仕事も生活もみんなで助け合う中で、まるで家族のような絆(きずな)が生まれましたね。
南極ではどんなものを食べていたのですか?
半田さん
昭和基地の中では、意外と豪華(ごうか)な食事を食べているんです。もちろん新鮮(しんせん)な食品は少ないですが、ボリュームのあるメニューが出てきます。プロのシェフが作ってくれるので、おいしいですよ。娯楽(ごらく)が少ないので、みんな食事が楽しみなんです。
白濱さん
機械の部品だけではなく、食料や生活用品なども1年分をまとめて「しらせ」が運んできます。追加はありません。生野菜や果物、たまごなどは時間がたつと悪くなってしまうので、早めに食べ終えてしまいます。だから南極生活も後半になってくると新鮮なものが食べたいなぁと思っていました。
栗崎さん
1年ぶりに「しらせ」が来ると、まずはたまごかけご飯を食べるんです。それがおいしいんですよね。

森戸さん
昭和基地の中でも少しだけ野菜を育てています。水耕栽培(すいこうさいばい)でかいわれ大根やキュウリ、もやしなどを作っていてそれを食べたりしますね。お酒やソフトクリームもありますし、おかしもたくさんありました。おせんべいやチョコレートが人気でしたね。
南極の思い出を教えてください。
白濱さん
わたしは相棒(あいぼう)ができたのがうれしかったですね。年も同じでたん生日も近く、とても気が合っていつも一緒にいました。同期の隊員たちとはみんな仲良くなって、帰国後も年に1回はみんなで集まっています。
栗崎さん
日本にいたら知り合えないような、いろいろな分野のプロフェッショナルと一緒にすごせるのも観測隊ならでは。南極では、仕事も生活も自分1人ではなにもできないですから、同期の隊員たちとの絆はとても強くなりますよね。
森戸さん
仲間がいたから乗りこえられましたね。助けてもらうこともたくさんありましたし、仲間を助けたこともあります。スノーモービルが崖(がけ)から落ちそうになったと連絡(れんらく)を受けて、急いで助けに行ったことをよく覚えています。
半田さん
南極での日々ももちろん思い出深いのですが、わたしは帰国の時に「しらせ」の中から見たシドニーの街の灯りが印象(いんしょう)に残っています。できるだけ人間の文明を持ちこまない南極での1年、そして昭和基地を出発してから約1ヶ月の船旅を終えて、ようやく人間界に帰ってきたぞ、と実感しました。